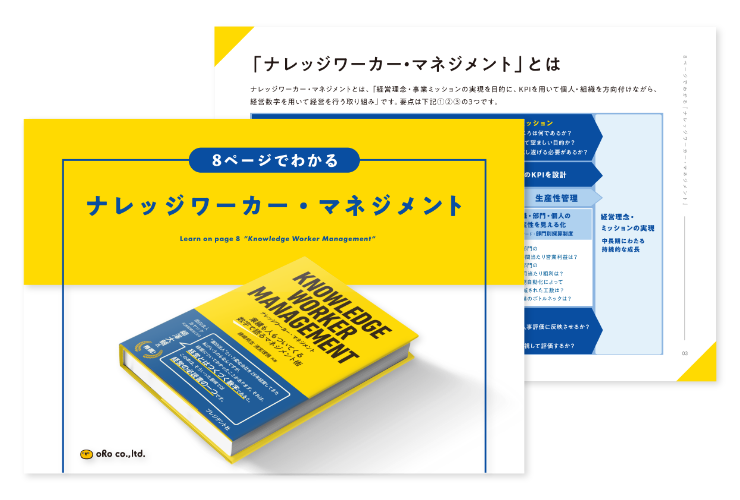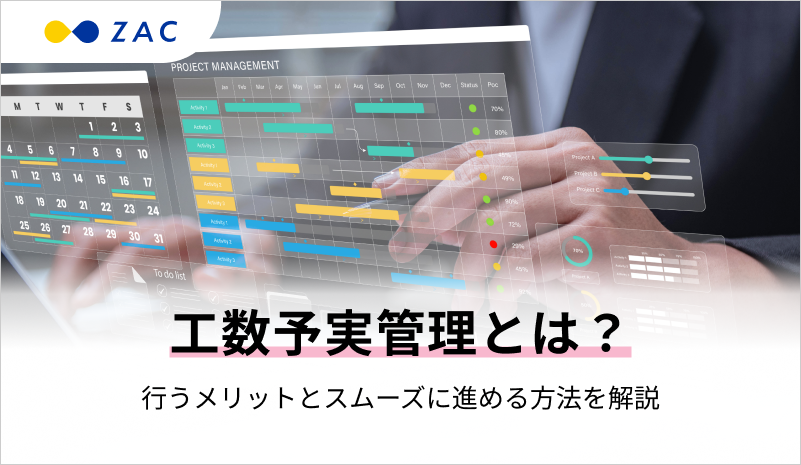事業の成長と社員の幸せは両立できる-なぜ『ナレッジワーカー・マネジメント』は顧客の共感を集めるのか-

2025/10/31公開
書籍『ナレッジワーカー・マネジメント 業績も人もついてくる 数字で語るマネジメント術』(以下、ナレッジワーカー・マネジメント)は、ナレッジワーカーこそが経営資源である知的サービス業の事業成長に必要なマネジメント術を体系的に解説した一冊です。
執筆の背景には、前事業部長・藤崎氏と、現在の事業部を率いる常務執行役員・事業部長の清宮氏が携わっており、長年にわたり知的サービス業の経営課題と向き合ってきた経験と、オロ自身が連続増収・黒字経営を続けてきた実践知がありました。
今回は本書の共同著者であり常務執行役員・事業部長の清宮氏に出版の想いを、また営業としてクライアント企業の経営課題に日々向き合う櫛田氏・藤田氏に書籍の反響をインタビューしました。
著者が語る、書籍に込めた「想い」
クラウドERP「ZAC」を提供するオロがなぜ、経営管理・マネジメントの書籍を出版するに至ったのでしょうか。その背景にある強い問題意識と、書籍に込められた「想い」について、著者本人に尋ねました。
『ナレッジワーカーマネジメント』の出版に至った理由を教えてください。
清宮:これまでお会いしてきた経営者は皆、事業をもっと成長させたい、より良い会社にしたいという高い志を持っていました。一方で、IT・広告・コンサルティング業といった知的サービス業に特化した経営ノウハウは、それほど世の中には出回っていません。特に生産性を高めるフェーズに入った企業では、数値管理の重要性に気が付いても、理想とする管理が実現できないだけでなく、そもそも理想形のイメージを持てていないことすらあります。
そのせいか、創業以来の連続増収・黒字経営を実現している当社の経営管理ノウハウを紹介すると、「うちもオロさんのような管理をしたい」と喜ばれることが多くありました。中でも「ガラス張りの経営を実現し、数値管理を徹底して生産性を高めることは、事業の成長だけでなく、昇給という形で社員の幸せ・喜びを増やすために必要」という当社の考え方には多くの驚き・共感をいただいてきました。
当社はZACを用いて管理会計を実践していますが、ZACはあくまでも管理会計のためのツールでしかありません。より踏み込むと、管理会計ですら、経営理念や経営者の志といった目的を実現する手段に過ぎません。そのため管理会計のあり方に唯一絶対の正解はないと考えています。それでもなお、20年以上の経営経験に基づき、経営者の志を実現するための考え方と実践ノウハウを提供することは、知的サービス業の経営者から共感を集め、最終的に当社の事業ミッションである「ホワイトカラーの生産性向上」が実現できると信じて、この度の書籍出版に至りました。
「数字の見える化」を重視するのはなぜですか。
清宮:会社や事業を持続的に成長させるには、生産性の向上が不可欠だからです。たとえ売上が伸び、社員が増えていても、生産性が高まっていなければ、それは単なる膨張でしかありません。企業の成長と膨張は似て非なるものです。生産性の向上を伴う成長を実現できてこそ、優秀な人材の採用・育成や事業開発などの成長投資のほか、昇給・賞与といった社員への利益還元に必要な原資に厚みが生まれてきます。
生産性を高めるには、経済合理的な判断が必要です。ほとんどの知的サービス業において、経営資源は即ち人材であり、いかに優秀な人材を採用・抜擢し、いかに主力事業・成長領域に優秀な人材をアサインするかが経営の肝であると考えています。
しかしここで、我々は何をもってある人材を「優秀」と評価するのかという問題が生まれます。
経済合理的に考えると、優秀な人材とは、生産性が高い人材、業績に寄与する人材となります。ただ実際には、数字で成果を把握しやすい営業部門はまだしも、制作部門、たとえばエンジニアやデザイナーの能力を、生産性の観点から横並びで評価している企業はまだ少ないように思います。数字のモノサシがなければ「夜遅くまで頑張っている人」「立派なクリエイティブをつくれる人」が闇雲に評価されがちですが、感覚的に"優秀"と思っていた人材は、売上に見合わない稼働をして案件の利益を食いつぶしているかもしれません。
もちろん数字だけで人材の優劣は語れないため、数字以外の部分、たとえば人間性や経営理念の体現度といった領域は、人事評価制度でのカバーが必要です。しかし先ほど述べた通り、制作部門の生産性評価をはじめとして、そもそも数字で語る土台が整っていない企業が非常に多いのが実態です。経営を数字で見える化するには、部門ごとに分断された業務の一元化から始まり、売上予測・原価見積の精度向上や、部門別採算制度の導入といったステップが必要になりますが、それらの段階的な取り組みによって得られる果実はあまりにも大きいと考えています。
執筆にあたってのこだわりを教えてください。
清宮:机上の空論で終わらせないことです。本質的で普遍的なフレームワークを示すとともに、各社でそれを実践するための具体的なノウハウをできるだけ詳細に書き記すことに注力しました。
第2章では知的サービス業での管理会計が難しくなるポイントを説明し、第3章ではそれらの障壁を乗り越えるための処方箋を提示しています。そのうえで第4章では実践例として、当社のKPIツリーや組織体制、評価制度などを解説しています。「オロを真似してください」と言いたいわけではなく、本書の内容を自社で応用する際のヒントとして提供しています。数値管理体制の構築に苦慮されていたり、管理会計のレベルをアップさせたいと考えている方にはぜひご一読いただきたいです。
営業が語る、書籍を手にした現場の声
クライアント企業との面談において本書の思想はどのように受け止められているのでしょうか。日々お客様と向き合い課題解決の最前線に立つ営業担当者に、リアルな反響を伺いました。
書籍はどのようなクライアントに喜ばれていますか。
櫛田:事業の立ち上げフェーズを過ぎて、組織が形になってきたクライアント企業に特に喜ばれています。売上は順調に伸びているものの、「今以上に成長するには利益率や生産性も意識しないと」と考え始めている方は、書籍の考え方に「なるほど」と共感されていますね。商談の場や展示会で書籍をお渡しすると、会社の次の成長に向けて具体的に動こうとしている方は興味を持って読んでくださっています。
書籍への反応で印象的なエピソードはありますか。
藤田:数値管理には「目的の定義」が必要、という記載にハッと気付きを持たれる方が多いですね。展示会でも、数値管理に取り組んでいるクライアント様が「目的不在のまま、ただ数字を集めただけになってしまっている」と話されていたのが記憶に残っています。商談の場でも「まず目的を整理してから管理体制を作ることが大事だよね」と盛り上がることもあります。
櫛田:担当者様が「会社をもっと良くしたい」と考えている場合、社内啓蒙のために、お渡しした書籍を社内で回し読みしてくれることがあります。私のクライアント様では、担当者様に渡した書籍が社長にまで届き、内容に共感してくださった社長から直々に管理体制の改善に向けた号令が出てプロジェクトが動き出したケースもありました。部長クラスでも、それまで課題意識を持っていなかったものの、熱意のある担当者様から回ってきた本書をきっかけに数値管理を自分ゴトとして捉えて改善するきっかけになった、という事例も伺っています。
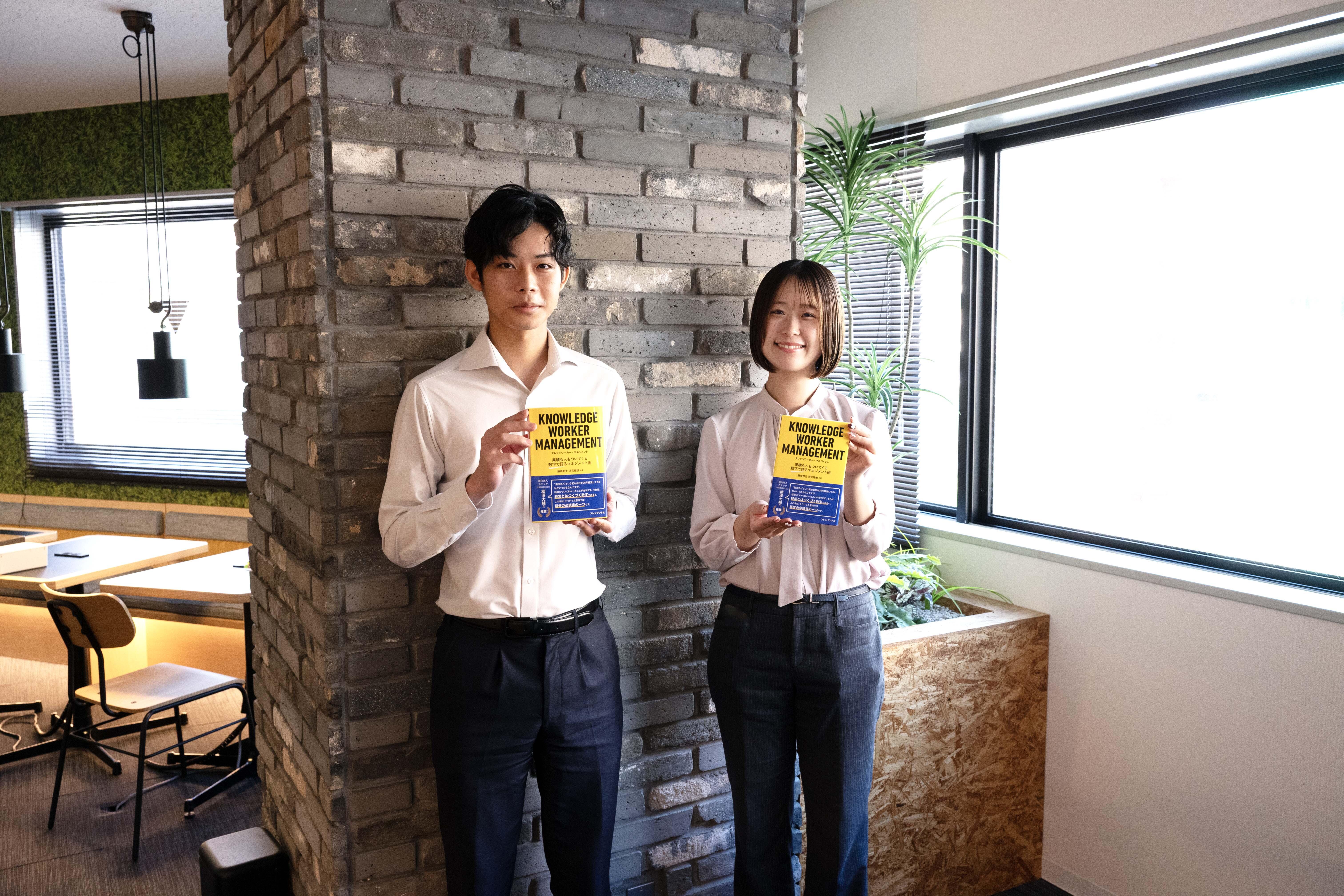
まとめ
『ナレッジワーカー・マネジメント』は、事業の立ち上げフェーズを終え、次の成長ステージに向き合う企業にこそ強く響く一冊です。目先の売上拡大だけでなく持続的な利益拡大・生産性向上にも目を向ける会社様にとって、経営と現場が同じ方向を目指し、組織が一枚岩となって成長を目指すための共通言語として数値管理を捉え直すヒントとして本書は活用されています。事業・組織に更なる成長を導きたいと考えている方は、ぜひ一度手に取ってみてください。