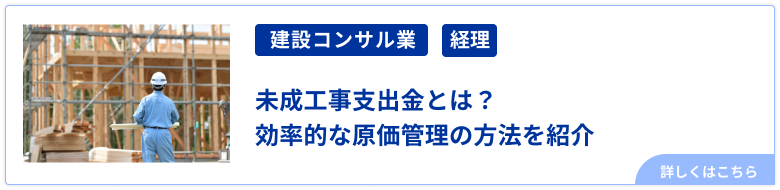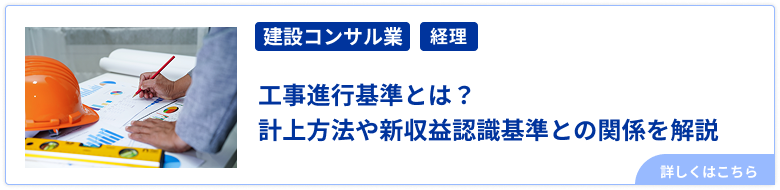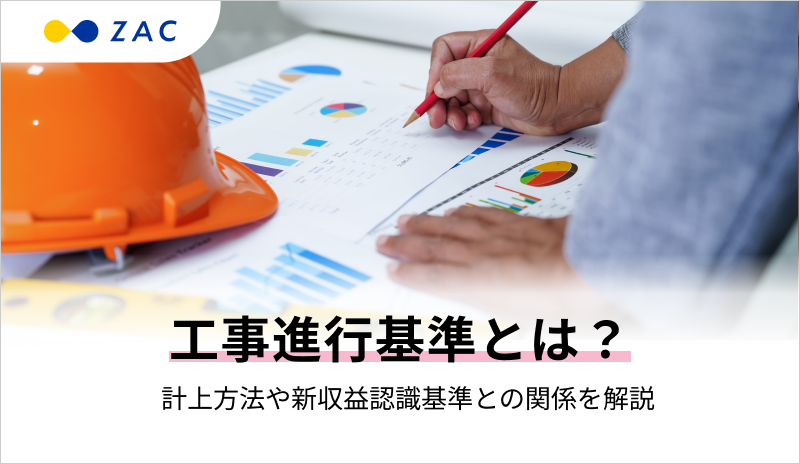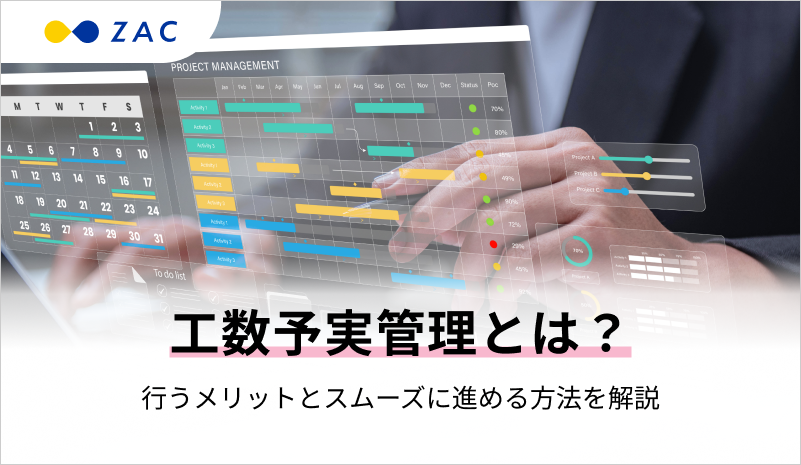工事原価とは?4つの構成要素と管理方法を解説

2025/5/23公開
建設業では1つの企業で複数の長期工事を抱えるのが一般的です。その工事にかかる原価を適正に把握することが、正確な会計処理の第一歩です。
そこで、本記事では、工事原価の定義や構成要素、適切な管理方法について解説します。正確で効率的な工事原価管理には、システムの利用も有効です。工事原価管理におすすめのシステムも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
工事原価とは
工事原価とは、建設業における勘定項目のひとつで、工事やプロジェクトの完成に必要なコストの総称です。工事原価を正確に管理することは、建設業において利益を正確に把握することでもあり、適切な価格設定や予算管理を行うために不可欠なものでもあります。
工事やプロジェクトが完了して得られた売上から工事原価を差し引くことで、利益を明確ににできます。ここからは工事原価を算出するうえで重要となる「完成工事原価」と「未成工事支出金」の2つについて、詳しく解説します。
完成工事原価
完成工事原価とは、一般会計でいう「売上原価」のことです。材料費、労務費、外注費、間接費など、工事に直接・間接的に関わるすべてのコストが含まれ、当該年度の損益計算書に計上されます。
工事が完了した時点で完成工事原価を集計し、その年度に発生した収益から差し引くことで、企業として得られた利益を把握できます。
未成工事支出金
未成工事支出金は、進行中の工事にかかる費用を記録するための勘定科目です。建設業特有の会計処理で、他業種では「仕掛品」にあたります。
工事が完成するまでの間に発生した費用が「未成工事支出金」です。完成後に適切な収益・費用を認識するために用いられます。
未成工事支出金について、詳しくはこちらの記事を参照してください。
工事原価を構成する4つの要素
工事原価は、「外注費」「材料費」「経費」「労務費」の4つの要素で構成されています。それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
外注費
外注費は、工事の一部を外部の専門業者や協力会社に委託する際に発生する費用を指します。具体的には、設計、施工、設備工事、専門技術者の派遣など、外部リソースを活用する際の契約金額や報酬などです。
近年では、自社の人員だけで工事を完了させるケースは少なく、外注費は工事原価の中で大きな割合を占めることが一般的となっています。
材料費
材料費は、建設現場で使用される資材や部品の購入費用を指します。具体的には、コンクリートや鉄骨、木材、塗料、配管など、工事の進行に直接必要な物資の費用です。
この費用は、工事の規模や仕様、資材価格の変動によって大きく異なるため、適切な調達計画と管理が求められます。
経費
経費は、材料費や労務費以外で工事に必要な費用を指します。具体的な項目は、設計費や現場の水道光熱費や通信費、材料の運搬・現場保管に伴う費用、減価償却費などです。
労務費
労務費は、工事を実施するために必要な人件費を指します。具体的な項目は、現場作業員や技術者、監督者の給与、賃金、手当、社会保険料などです。直接工事に携わる作業員の人件費だけでなく、現場監督や安全管理者など、工事に間接的に関与するスタッフの人件費も含まれる場合があります。
ただし、工事に関係のない管理部門の給与などは販売費及び一般管理費に分類されるため、工事原価に含まれません。
工事原価率とは
工事原価率とは、建設業における工事の売上高に対する工事原価の割合を示す指標のことです。以下の計算式で算出できます。
- 工事原価率=工事原価(売上原価)÷完成工事高(売上高)×100%
中小企業実態基本調査(令和4年度の決算実績)によると、建設業全体での工事原価率の平均は76.1%(*1)でした。自社の工事原価率を分析する際は、この平均値と比較するのも一つの手段です。
なぜ工事原価管理は複雑で難しいのか?
建設業の工事原価計算は、一般的に複雑で難しいと言われています。その理由は主に以下の4点です。
一般会計と異なる勘定科目を扱うため
建設業は、他の業界と異なる特有の勘定科目が存在します。具体的には、以下の勘定科目が挙げられます。
- 完成工事高
- 完成工事未収入金
- 工事未払金
- 未成工事受入金
- 未成工事支出金
特に、一般的な工事は長期にわたるため、期間中にかかった費用をすべて未成工事支出金として計上しなければならない点に注意が必要です。
しかし他の業界には存在しない費用項目であるため、計上すべき勘定科目を誤ったり、集計に時間がかかったりします。
コストの種類が多岐にわたる
上述したように、工事原価は複数の費用項目で構成されています。さらに、それぞれの項目において細かい内訳が存在するため、正確に集計・管理できるかどうかが大きな課題となります。
また、異なるタイミングで費用が発生するため、リアルタイムで把握することが困難なのも管理の難しさの要因です。
工事進行基準の考え方への対応が必要
工事を進行しながら、進捗に応じた収益や原価を分割計上する「工事進行基準」の考え方が適用される場合があります。長期かつ大規模な工事の場合は、強制適用となる考え方のため、事業規模によっては対応が必須です。
この基準に基づく計算は、進捗率の算出や収益認識のタイミング調整などが必要となるため、経理業務において高度な専門知識が求められます。会計処理の手間も増え、煩雑になってしまうことが懸念点です。
工事進行基準については、以下の記事を参照してください。
工事ごとの個別原価管理が難しい
建設業では、複数の工事が同時に進行していることが一般的です。工事(プロジェクト)ごとに個別原価計算が必要であるため、それぞれの費用を適切に工事に紐付けなければなりません。そのうえで、全体の収支バランスを把握しなければならないため、工事原価管理は非常に難しい作業となります。
工事特有の事情として、一例として以下のような点が個別原価管理を複雑にしています。
- 工事に使用する共通の器具類のコストをどうするか
- 塗料や薬剤など、現場で使用量の正確な把握が難しい材料がある など
こうした事情から、どの費用がどの工事に紐づくのかを、経理担当者と実務担当者間で連携し、日々タイムリーに共有しなければなりません。
工事原価を正しく管理する方法
工事原価の正確な管理は、工事(プロジェクト)の成功に直結するため、非常に重要です。正しい原価管理を実現するためには、以下のポイントに注意しましょう。
コストの種類を明確に分類する
工事費用の分類について上述した通り、どの費用がどの項目に該当するか正確に分類することが重要です。あらかじめ費用を明確に分類できていれば、どのコストがどの工程で発生しているか把握しやすくなり、予算管理の適正化につながります。
工事進行基準の考え方に基づいた費用認識をする
かつては、工事が完了した時点で帳簿に一括計上する「工事完成基準」が一般的でした。しかし2009年4月から、「工事進行基準」に基づいた分散計上の考え方が原則となったため、進行中の工事に対して適切に利益や費用を認識することが求められるようになりました。
工事進行基準の考え方に対応することで、工事の進捗状況に合わせたリアルタイムな原価が把握可能となり、工事が終わってから予算がオーバーしていたことに気付くといったケースを防げるようになります。
工事原価管理システムの活用
建設業には、未成工事支出金のような特有の勘定科目があり、工事ごとに個別原価計算が必要です。複雑な個別原価計算や工事(プロジェクト)ごとの個別管理を効率的に行うためには、専用ツールやシステムの活用をおすすめします。
個別原価計算の自動化やリアルタイムの進捗把握が可能となるため、管理業務の負担を軽減できます。ミスや漏れも削減可能です。
工事進行基準に対応した効率的な原価管理を実現するならZAC
建設業特有の原価管理や会計業務に対応したシステムにも、さまざまなものが存在します。本ブログを運営する株式会社オロのクラウドERP「ZAC」も、建設業特有の会計処理や工事進行基準の考え方に対応しています。
工事(プロジェクト)ごとの進捗状況に応じた原価管理を実現できるので、リアルタイムな進捗とコストが把握可能です。さらに、工事の収益や費用を正確に認識できるようになり、各プロジェクトの予算管理や原価計算を効率化できます。
今後システムによる原価管理を検討しているなら、ZACのような工別原価計算に対応したシステムを利用することがおすすめです。
まとめ
建設業では、特有の勘定科目や会計処理が求められるため、工事原価を適正に管理することが重要です。その一方で、他業種と異なる会計処理やコストの種類が多いことから、工事原価管理は社内の課題にもなりえます。個別原価計算や工事進行基準の考え方への対応には、高度な知識と慎重な対応が求められるため、煩雑に感じられることもあるでしょう。
そのため、建設業の会計処理においては、あらかじめ費用の分類を明確にしたうえで、タイムリーかつ正確なコストの把握を行うことが重要です。工事原価管理を効率化するには、専用の原価管理システムの導入をおすすめします。ZACのように、建設業に対応したシステムを利用することで、ミスや漏れのないタイムリーな工事原価管理が実現できます。