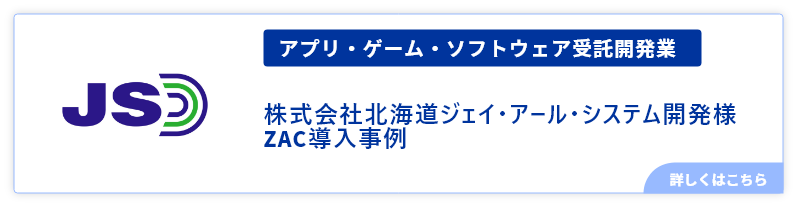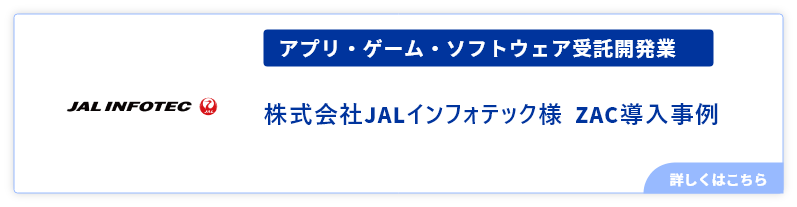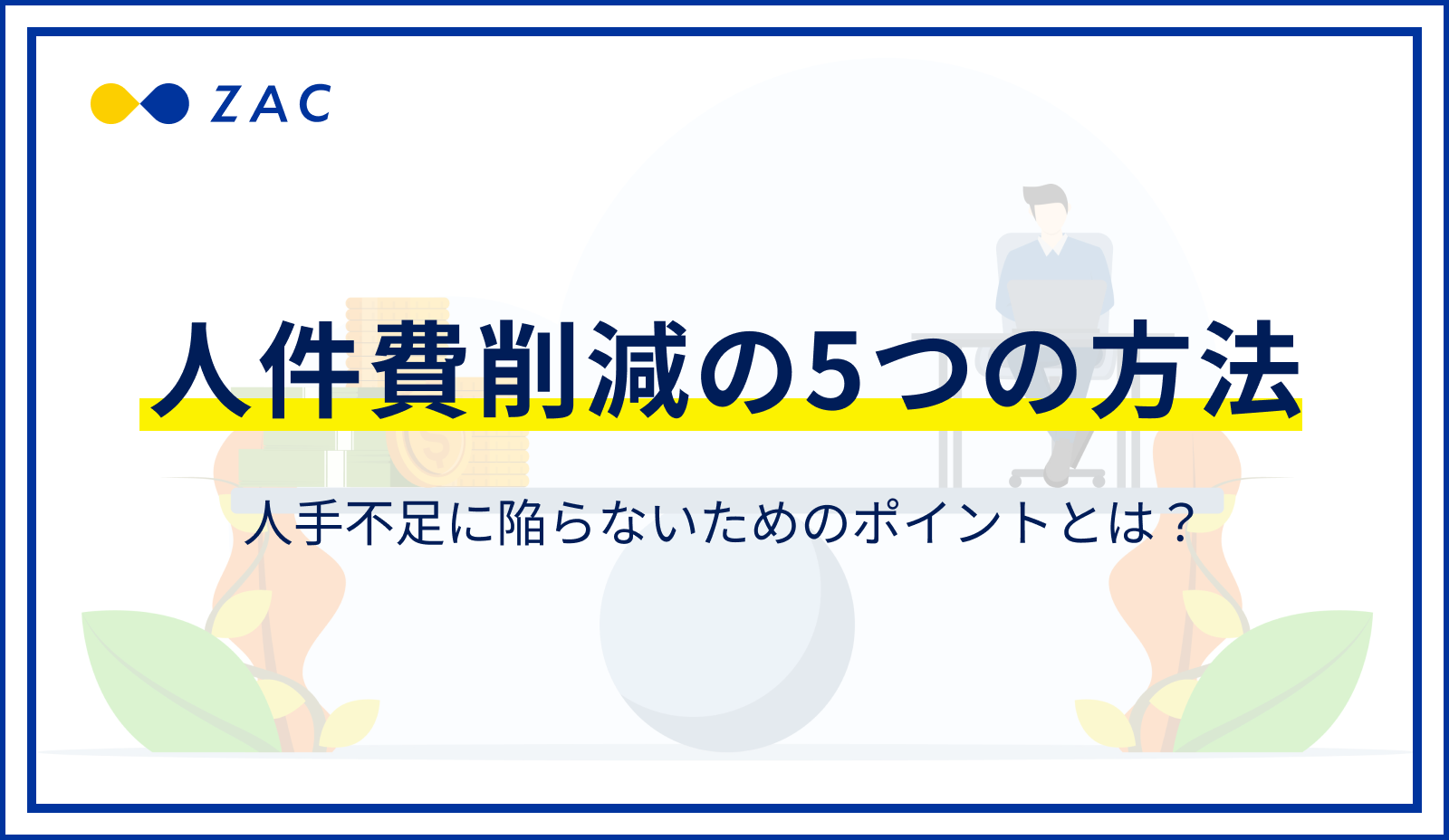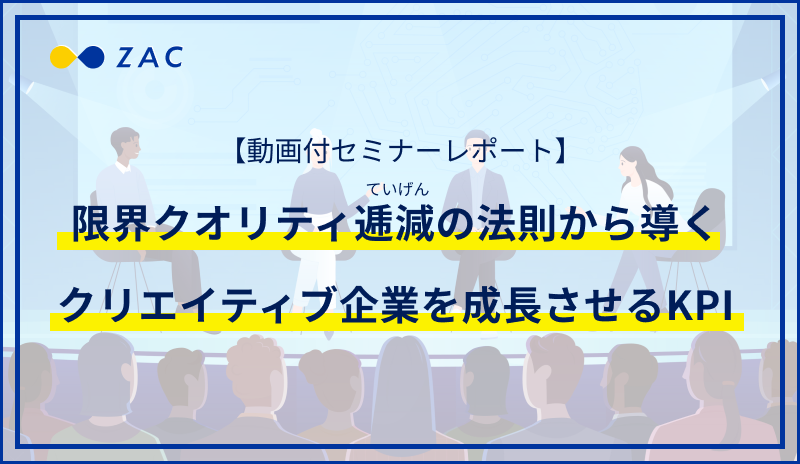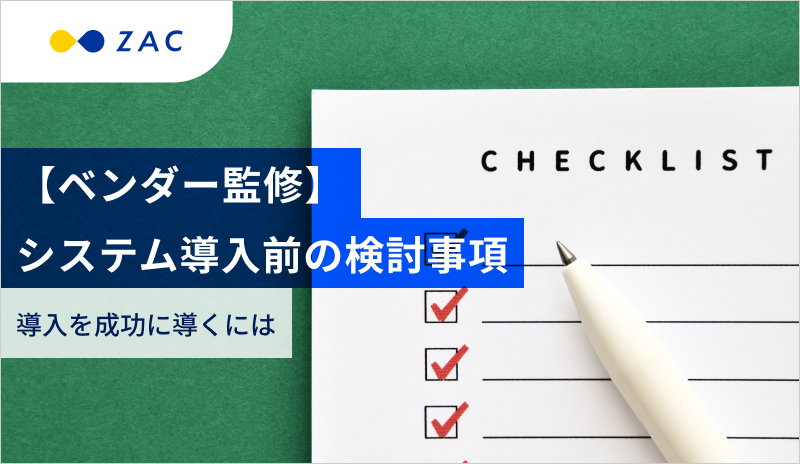BPR(業務改革)とは?進め方や業務改善との違いについて解説!

2021/12/14公開2023/7/14更新
BPRとは、業務プロセス全体を抜本的に見直し、新しい業務プロセスを構築することを言います。日常的な業務プロセスの中で課題を見つけ改善を繰り返す業務改善とは異なり、新しいプロセスを構築する点はまさに「改革」と言えるでしょう。
BPRを行うことによって、社内の生産性向上が期待できるほか、製品やサービスの品質向上、従業員満足度の向上、意思決定のスピードアップなど、社内外でさまざまなメリットを得られます。本記事では、業務改善やDXとの違い、BPRの進め方などについて詳しくご紹介します。
目次
BPR(業務改革)とは?
BPRは「Business Process Reengineering」の略称で、日本語で業務改革のことです。従来の業務プロセスの課題を抽出し、業務の進め方や情報共有のしかた、組織のありかた、導入している情報システムなど、業務プロセスの課題に関わるものを再構築していくという考え方を指します。
BPRはもともと、マサチューセッツ工科大学のマイケル・ハマー教授と経営コンサルタントのジェイムズ・チャンピーの著作『Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution』(1993年)で提唱された考え方です。邦題では『リエンジニアリング革命』としても出版され、その考え方は日本にも広がっています。
『リエンジニアリング革命』では、コストや品質、スピードといったパフォーマンスに重要な要素を劇的に改善するため、ビジネスのプロセスを根本的に再考しデザインすることを「リエンジニアリング」と呼んでいます。
BPRと業務改善の違い
BPRと業務改善はよく混同される概念ですが、意味は大きく異なっています。 業務改善とは、あくまで課題が見つかった業務の一部を改善することです。また、業務を進めながら少しずつ改善を施していくため、「業務の部分的な課題を少しずつ修正していく」と理解しましょう。 一方で、BPR(業務改革)は、その名の通り業務の抜本的な「改革」を行います。BPRが目指すものは抜本的で劇的な効率化であり、業務プロセスを1から見直すことになります。 BPRは業務プロセス全体を改革対象にするため、必然的に部署間にまたがる業務や組織のありかたといった大きなテーマを扱い、会社全体で取り組むことが求められます。
BPRとDXの違い
会社全体での改革という点において、BPRと混同されがちな言葉にDXがあります。DXは「Digital Transformation」の略で、デジタル技術によってビジネスモデルや企業そのものに改革を起こすことを指します。一方のBPRは、業務プロセスに特化した改革です。ビジネスモデル自体を変えるのではなく、業務プロセスを改革してビジネスにアプローチしていきます。そのため、DXの一環としてBPRが行われる場合もあるでしょう。
BPRを行うメリットとは
BPRによって業務プロセスを改革することで、企業にはさまざまなメリットが期待できます。具体的なメリットは以下の通りです。
生産性の向上
BPRによって業務プロセスの課題に対策を講じ、ムダを排除できれば、業務の効率化が図れます。スムーズな業務遂行が可能になることで、生産性の向上が期待できるでしょう。
BPRは部署ごとではなく、企業全体で行われることも特徴です。業務を俯瞰で見ることで、部署にまたがる課題を発見でき、部署間の連携も取りやすくなります。その結果、企業全体の業務が最適化されるのです。
コスト削減
業務プロセスを見直すなかで、ムダな工程の削減やリソースの最適化を行えば、コスト削減にもつながります。たとえば、システムをクラウド化するといった改革を行えば、これまでオンプレミスシステムにかかっていた保守管理費を減らせるでしょう。
また、残業が多い部署があったとしても、人的リソースを適切に配分できれば、これまでかかっていた残業代を削減できる可能性もあります。BPRの実施自体にもコストがかかりますが、長期的に見ると企業にとってはプラスになるでしょう。
製品・サービスの質向上
業務を効率よく行えるようになることは、自社だけでなく、製品やサービスの質向上といった顧客へのメリットにもなりえます。たとえば、社内における承認・申請手続きや情報共有のための定例会議を見直し、ムダな時間を削減することで、メインの業務に注力できるようになります。その結果、製造・開発であればより良い製品を作れ、顧客対応であれば的確な対応をよりスピーディに行うことが可能です。
属人化の防止
属人化し、特定の人しか担当できないとされていた業務も、業務プロセスを見直すことで標準化できます。業務を誰もが行えるようになれば、担当者の不在による業務停滞のリスクを避けたり、一部の人に偏っていた業務負担を解消できたりといった効果が得られます。業務フロー全体を見通せるようになるため、社員の業務量を把握して休暇取得を促すといった対応も容易になり、従業員満足度も向上するでしょう。
意思決定のスピード向上
日々変化が著しいビジネス環境の中、自社の競争力を高め、優位性を得るためには、適切かつスピーディな意思決定が求められます。BPRによって意思決定フローもシンプルになり、経営判断のスピード上昇が期待できます。
BPRの4つの要素
次に、BPRの定義に内包される4つの要素を見ていきましょう。BPRを成功させるためには、この4つの要素を含む改革であることが必要です。
①根本的
「根本的」とは、従来の業務をなぜ実施しているのか、大元の理由を明らかにするという意味があります。 特に歴史の長い会社は、業務を根本的に見直す機会がなくなり、仕事の効率性が失われてしまっている可能性があります。現在の業務の必要性を問い直したり、組織の現在の体制は合理的なのかを考えるなど、根本的な見直しが求められます。
②抜本的
「抜本的」とは、時代にそぐわない要素を捨てさり、慣習的に進めてきた業務を本当に必要な業務だけにすることとされます。 例えば、「従来から決められた方法がある仕事だから」といった理由で見直しがされない業務プロセスや組織構造は、結果的に非効率な結果を生み出す可能性があります。 客観的に見直すことが、「抜本的な」改革なのです。
③劇的
「劇的」とは、インパクトの大きな改善をすることです。 業務改善が「部分的」な改善であるのに対し、BPRは最大限効果のある改善を行うことが目的であり、この点が両者の違いでもあります。 業務プロセスや組織のありかたを、大胆に変化させることで、「劇的な」効果が期待できるのです。
④プロセス
「プロセス」は、仕事の手順、人員配置、役割分担などの変更、仕事のやり方をプロセスとして定義することで、業務遂行の仕組みを構造的に変更することを言います。 日本企業は意思決定プロセスが複雑化、煩雑化しやすいことが指摘されています。BPRによって顧客志向のプロセスへと作り替えることで、企業の価値が高まることが期待できます。
BPRの進め方
BPRは、次のプロセスで進めていきます。
- ゴール設定
- 業務分析
- 設計
- 実施
- モニタリング・評価
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
ゴール設定
まずは、BPRを実施する目的と目標を設定する必要があります。何のために行うのか、またどこを目標として行うのかが明確になっていなければ、方向性を見誤ったり従業員のモチベーションが低下したりする可能性があるからです。まずは企業のトップ層で目的と目標を定めたうえで、BPRを行う業務範囲と業務単位を設定し、あるべき姿(To-Be)を描きます。トップ層がBPRで叶えたい夢を対象部署と共有することで、各従業員の「目標を絶対に達成しよう」という士気が高められるでしょう。
業務分析
次に、現在の業務フロー図や業務分担表を作成し、組織構造を明確にします。担当者名や作業工数、成果物名を記入することで、現状の課題やボトルネックを分析できるようになります。このとき、トップ層が考える課題だけでなく、現場の声を吸い上げて実務レベルの課題まで把握することが重要です。
設計
続いて、目標に沿って、実現したい業務フローを設計するフェーズです。具体的には、サービス提供のために必要なコア業務を並べ、現状分析で判明した課題を解決できるよう、業務フローを最適化します。
目指す業務フローを定めたら、どのような手順で業務フローを変えていくのか、スケジュールや担当者とともに計画を作成します。このとき、より効果が高いプロセスから着手するよう、優先順位も合わせて検討するといいでしょう。
実施
ここまでに設計してきたことを実施し、改革を進めていきます。このステップは長期にわたることが一般的です。実施していく途中で方向がずれてしまわないよう、定期的にBPRの目的や目標を振り返り、社内で連携しながら進めることをおすすめします。もし、実施している途中で方向転換が必要であれば、目的・目標を念頭において手段を変更することも視野に入れておきましょう。
モニタリング・評価
BPRを効果的に進める際に忘れてはならないプロセスが、モニタリングや効果測定です。 BPRは実施して終わりではなく、実施前と実施後でどの部分がどの程度改善したかを把握し、内部や外部に説明できるようにする必要があります。 例えば、稟議に関するプロセスを改革したことにより、どの程度顧客への対応が早まったのか、あるいはどの程度顧客満足度が改善したのかなど、具体的な数値で示せることがベストです。
BPRを進める際のポイント
BPRを進める際には、いくつか注意すべきポイントがあります。ここでは3点ご紹介します。
BPRに関するPDCAサイクルの確立する
BPRは常にPDCAを回しながら、より良い形になるよう適宜修正していくことが望まれます。 そのため、BPRのPDCAサイクル確立のために、できるだけ目標や成果を定量化し、実施後に誰もが客観的に評価できるような体制を整えておくことが求められます。 その意味で、BPRは実施前のKPI設定時から勝負は始まっていると言えます。
関係者の間で情報を共有する
BPRは会社が一丸となって取り組む大きな改革であり、社内の業務プロセスや組織のありかたを根本的、抜本的、劇的に変革するものです。そのため、業務フローを見える化し、BPRの意義や現状・課題、BPRによって改善後にどのような会社の姿がイメージできるのかなどを関係者間で共有することが重要です。 BPRを適切に推進するためには、会社のトップや役員クラス、取引先からも理解を得る必要があるでしょう。
「ゼロベース」で考えられているか
繰り返しになりますが、BPRは「根本的」「抜本的」「劇的」な変革が求められます。そのため、これまでなんとなく続けてきた業務プロセスの必要性についてももう一度考える必要があります。 特定の部署や人への忖度や見せかけの部分的な改善では良い成果は得られません。文字通り「ゼロベース」で改革を進められているか、その都度自分たちに問い直してみましょう。
BPRの具体的手法
実際にBPRを行うにあたって有効な手法を見ていきましょう。主に以下の3つの手法が考えられます
- ERP
- BPO
- シェアードサービス
それぞれについて具体的に解説します。
ERP
ERPとは「Enterprise Resource Planning」の頭文字で、企業の持つ資源=「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」を一か所に集めて管理し、有効活用するという考え方、またはそれを実現するためのシステムを指します。社内に情報が分散されていると、業務が煩雑になり、経営判断の把握にも時間がかかってしまいます。ERPならば、各部門で独立して存在している期間システムを一元管理できるようになるため、データ管理の効率化や社内情報の可視化可能です。
BPO
BPOとは「Business Process Outsourcing」の頭文字で、企業における業務プロセスを一括して外部委託することを指します。プロセス全体を委託することから、業務の一部を切り出す「アウトソーシング」とは異なると言えます。企業の核となる業務ではなく、あくまでノンコア業務を外部に任せるという手法です。社内に専任者がいない部門の業務、負担が大きい業務などを、専門業者に委託できるため、より効率的に業務を進められるのがメリットです。
シェアードサービス
シェアードサービスとは、業務効率化や全体最適を目指して、類似業務をひとつに集約させるという考え方です。各部署や事業所、グループ会社等に散らばっていた経理や人事、総務といった間接部門の業務を集約して1部門で担当することで、業務を標準化し効率化が叶います。場合によっては、集約した業務を請け負うための子会社(シェアードサービスセンター)を設けることも一手です。
BPRの成功事例
ここでは、システムを活用することでBPRに成功した事例を紹介します。ERP導入により、紙での決済をシステム上でできるようになった事例と、内部統制の効いた業務プロセスを実現できた事例です。
株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発様
JR北海道グループ各社のICT基盤を支える、株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発様では、紙の書類での申請・承認が基本だったため、決裁に時間がかかっていたといいます。そこで業務効率化と内部統制強化を図るため、本ブログを運営する株式会社オロのクラウドERPシステム『ZAC』を導入。申請・承認フローがシステム上で行えるようになりました。申請の差し替えや必要なデータの確認が簡単になり、進捗状況も一目でわかるため、意思決定のスピードが向上したそうです。
株式会社JALインフォテック様
JALグループのIT中核会社として、先進的かつ効率的なITソリューションを提供する株式会社JALインフォテック様。基幹システムの老朽化対応を機に、ZACを導入しました。導入後は、営業の引き合いからプロジェクト完了までをシステム上で管理できるようになり、情報の集約化を実現。さらに、ワークフローに沿った業務進行ができるようになり、スムーズで統制の利いた業務プロセスに改革できたといいます。
まとめ
BPRは現在の業務フローを問い直すことが求められるものであるため、成功すれば社内の行き詰まりや閉塞感を打破できるでしょう。 しかし、BPRの遂行には既存業務の徹底的な見直しなど、大きな推進力が必要となり、場合によっては社内の反発も生じる「痛みを伴う改革」になるでしょう。 だからこそ、社内への周知や合意形成ができているかが成功のカギを握ることになります。 今回ご紹介したBPRの流れを参考に、社内の合意形成を図りながら適切なプロセスで改革を進めていきましょう。