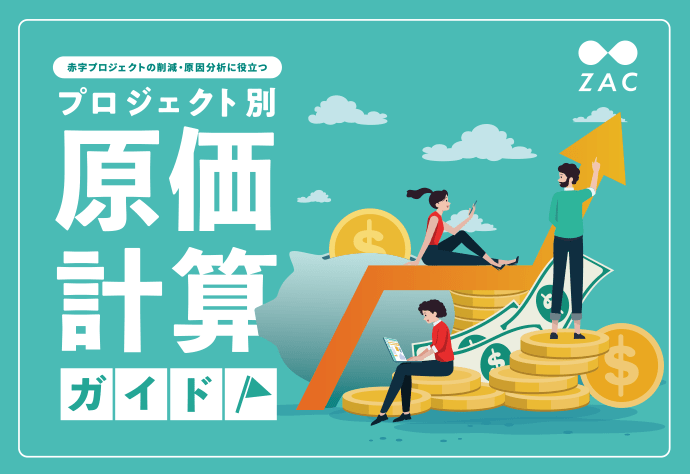上場審査と株価の算定書

2013/7/08公開
前回のコラムでは株価の計算方法について解説しました。
今回は、上場審査において必要となってくるであろう株価の算定書の必要性と、上場後においてどのような影響があるのかについて説明していきます。
目次
上場審査と株価の算定書
株式の上場審査においては、有価証券届出書の開示対象期間である上場申請直前期末から遡って5事業年度(決算期変更をしている場合は5年以上にわたる事業年度)内に株価を算定すべき事由(第三者割当増資、ストックオプションの発行、株式の譲渡など)が行われた場合には、その取引された株価の客観的根拠を会社側から幹事証券会社に対し示すことが必要となります。
この際、簿価純資産法などの余程シンプルな方法であれば、社内で算定書を作成して示すことも認められるでしょうが、時価を用いた方法やDCF法などによる場合は価格算定の客観性を保つ観点から第三者による算定書を用意することが求められますので、事前に注意が必要です。
第三者割当増資の株価が、その株式の時価から考えて著しく低い価格で行われた場合は、有利発行として株主総会の特別決議が必要であり、これを通常の発行として取締役会決議で行った場合は、発行自体が無効になる恐れがあります。この訴えは株主代表訴訟の時効にかかる期間まで可能なため株式上場後であっても7年を経過していなければ訴えられる可能性があることになります。こうしたことがあるので、幹事証券の審査部は株価の妥当性を確認するために算定書の提出を求めることになるのです。
なお、株価の鑑定書、評価書、算定書の違いに関しては、結果の厳格性の違いと考えてよいと思います。現在の実務では鑑定書は裁判などに際して必要な場合以外作成されることはないでしょう。上場関係の実務では従来評価書を作成していましたが、作成者側の主観や責任を軽減する意味合いで現在では算定書として作成されることが多いといえるでしょう。
上場前後の3種類の株価とは
株式上場直前に上場申請会社(発行体)あるいは株主から引受証券会社に流動化させる株を引受けてもらうわけですが、このときの価格を引受価格といいます。そして引受け証券会社はそれに7%程度の手数料を上乗せして投資家に対し公募価格を提示し購入の募集をします。そしてこのようにして事前に株主が作られた後に新規上場日となり、売り気配と買い気配が重なったところで上場初日の株価が決まります。この株価を初値といいます。つまり、引受価格、公募価格、初値の3種類の株価が上場前後に存在するわけです。そして公募価格と初値の乖離率のことを初値騰落率といい、証券界では重要な指標として利用されています。特に初値が公募価格を割ってしまった場合は、「公募割れ」といい、これの意味することは最初にその会社の株主になってもらった人がいきなり損をしてしまうことで、そもそも幹事証券による最初の値付けが甘かったのではないかと疑われることになるわけです。
一方で初値騰落率が100%(公募価格の2倍)など、著しく上がった場合には引受証券会社は値付けが厳しすぎなかったか発行体から批判を受けたりすることになります。実際のところ日本の証券会社では概ね初値騰落率が高くなった方が良いと考えていて、それは投資家が潤うことによって証券市場の活性化につながると考えているということでしょう。このことは証券業界で年間の新規上場会社については初値が公募価格を上回った割合を勝ち率、下回った割合を負け率と称してデータを集計していることからも分かります。
2000年から2005年にかけて初値騰落率は総平均で見て上昇を続けました。中でも2004年の平均値は100%であり、2005年は134%となり、つまり新規上場株を公募価格で入手すれば平均でも2倍以上になるというすごいことになっていたのでした。この2年間における公募割れ銘柄は5%程度つまりほとんどの銘柄が買えれば得をするという状況だったわけです。このブームは2006年まで続き2007年以降徐々に冷え始め2008年には22%まで下落した後、2009年35%、2010年24%、2011年22%、2012年49%と回復傾向にあります。
なお、発行体側が引受価格を上げるように極端な圧力を欠け、引受証券会社がそれに屈して理論価格を著しく上回る株価で引受けたという理由で2007年3月にエイチエス証券が金融庁より処分を受けています。これは業界では有名な事件ですが処分を受けた証券会社より圧力を加えた当事者の会社が非難されるべきで、本来上場資格などない会社ということが言えるでしょう。この会社は当然上場後すぐに株価は下落し、投資家にも大きな損失を与えることとなりました。
発行体としても昨今のような株式市場の状況では引受証券会社から提示される株価を知って愕然とすることは有るでしょう。もちろん引受証券会社も最初から提示した価格で限界ということは無い可能性が高いですから、交渉の余地は残されているでしょうが、社会通念から考えて限度を超えたことをすれば、エイチエス証券のようなことになってしまうでしょう。上場時の株価が全てではありません。株式が上場していればその間は株価は付き続けるわけですから、上場時の株価などは一過性のものに過ぎないわけで、実力のある会社であれば、いずれはそれが認められた株価が形成されるはずで、むしろ最初から過大評価されてしまう方がリスクが高いと考えるべきでしょう。
上場してからの株価がどのように形成されるかについては、やはり将来価値的な要素が一番強く反映されるものと考えられます。したがって、上場して資本市場からの資金調達を重視する会社は将来評価が高い会社が好ましく、逆に一般的に優良会社といわれるかこの蓄積が十分にあって経営が安定しているような会社は上場しても思ったほどの高い株価にはならないという可能性が高いでしょう。
もっとも、高い伸び率ではないにしろ株式上場後10年とかの長期にわたり安定的に増収増益を繰り返してきたような会社は、徐々に評価を上げ高い株価を維持できるようになる可能性が高いといえるでしょう。
かつて日本に新興市場が出来る前、日本の会社にも直接アメリカのNASDAQなどに上場を勧誘する動きがありました。そのときに言われていたのはアメリカの金融マーケットは将来性のある会社については世界で最も高いバリュエーション(評価)をつけることができるということ。外資系のアンダーライター(引受幹事証券会社)はIPOプロジェクトのキックオフミーティングで我々の責任は如何にバリュエーションを上げることかにあると明言していました。このことは基本的には今も変わらないのでしょう。そして、アメリカではIPO時に放出する株の割合が日本よりも通常相当多いことにより(本当の意味でgo public なのです。)、アメリカのアンダーライターは株価をそれなりに抑制して馴染みの顧客に公募株を持っていくような日本的な商売手法ではなく、単純に発行体とアンダーライターの取り分が多くなるように、株
こうした傾向は、日本での事例としても外資が大株主で、上場時にそのかなりの持分を売出しするようなケースでは株価の設定が高すぎて、公募割れを起こしている事例が多いことなどからも推測できるでしょう。
現実にアメリカの金融マーケットが企業価値を最も高く評価するかどうかに関してはケースバイケースでしょうが、経済活動において全くアメリカ市場と関わらない会社であればアナリストも適切な評価を行うことが出来るとは考えられず、むしろカントリーリスクに関するディスカウントが行われると見るのが正しいでしょう。
また、IPO時に目いっぱいアクセルを踏んでもらって評価額を高くすることは、もしその評価が実際の実力を上回っていたとしたら後で破綻をきたすことになりかねないので決して喜んではいられないのです。
ここで発行体という言葉を使わせていただきましたが、これは主幹事証券会社が上場申請会社に対して使う別称で、彼らアンダーライターが引受ける株式を発行する会社の意味で使われます。
なお、アメリカでは、引受主幹事証券会社(アンダーライター)が日本のように審査をするということは行われておらず、法律事務所が企業内容精査(デューデリジェンス)を行い株式上場するに際してのリスク情報を記載し、それが新規上場に伴う発行株式の目論見書(プロスペクタス)のほぼ半分にもわたる量となるというのが行われています。また上場後の開示規制に関しても、日本のように取引所や金融庁(財務局)から行われるというのではなくSEC(証券取引等監視委員会)によって厳しく監督が行われています。