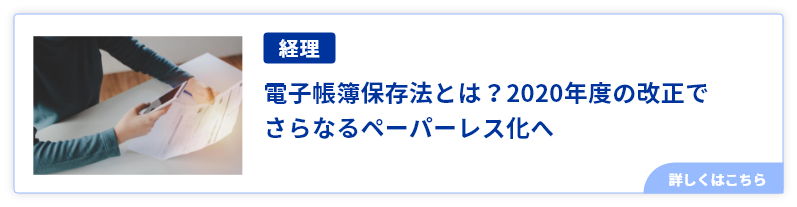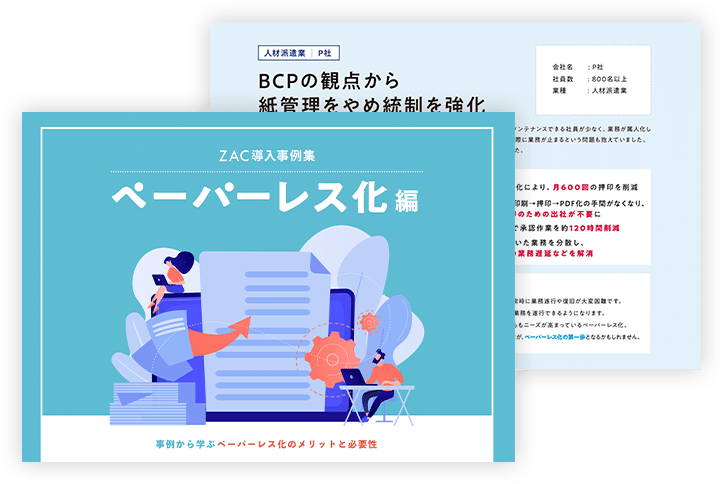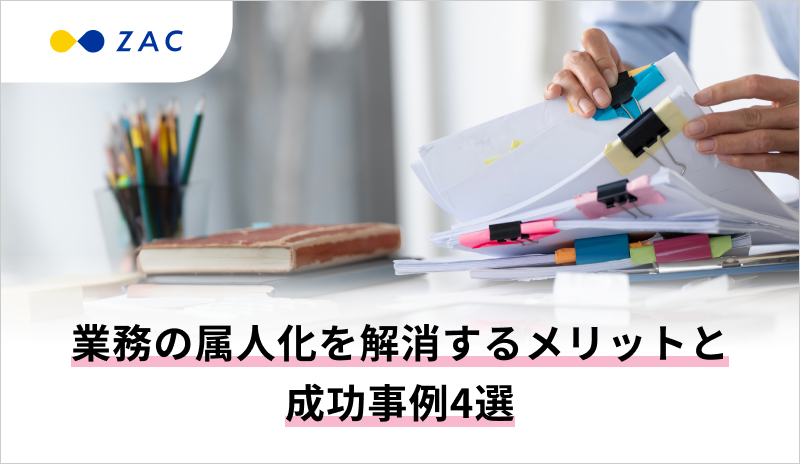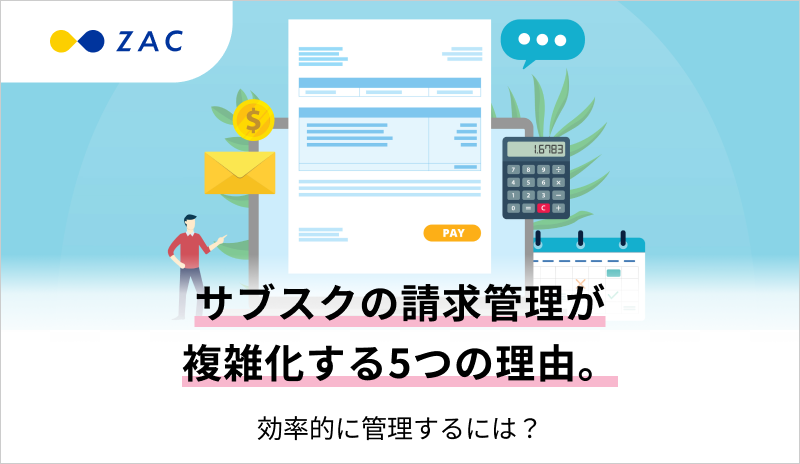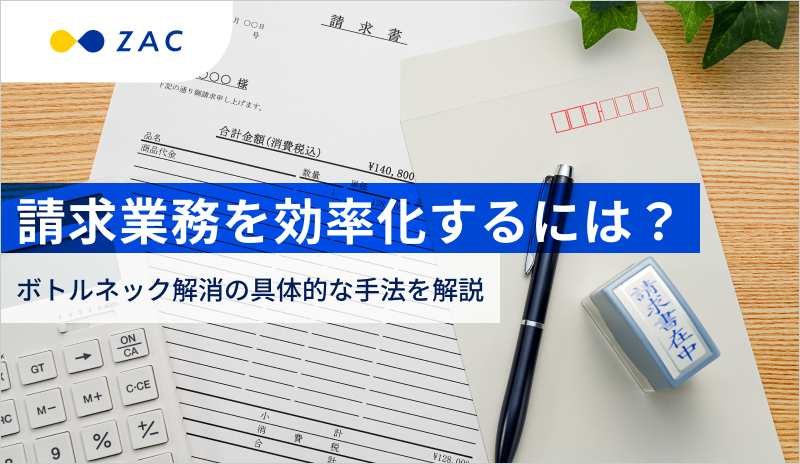コロナ禍で明らかになった、ペーパーレス化が必要なたった一つの理由
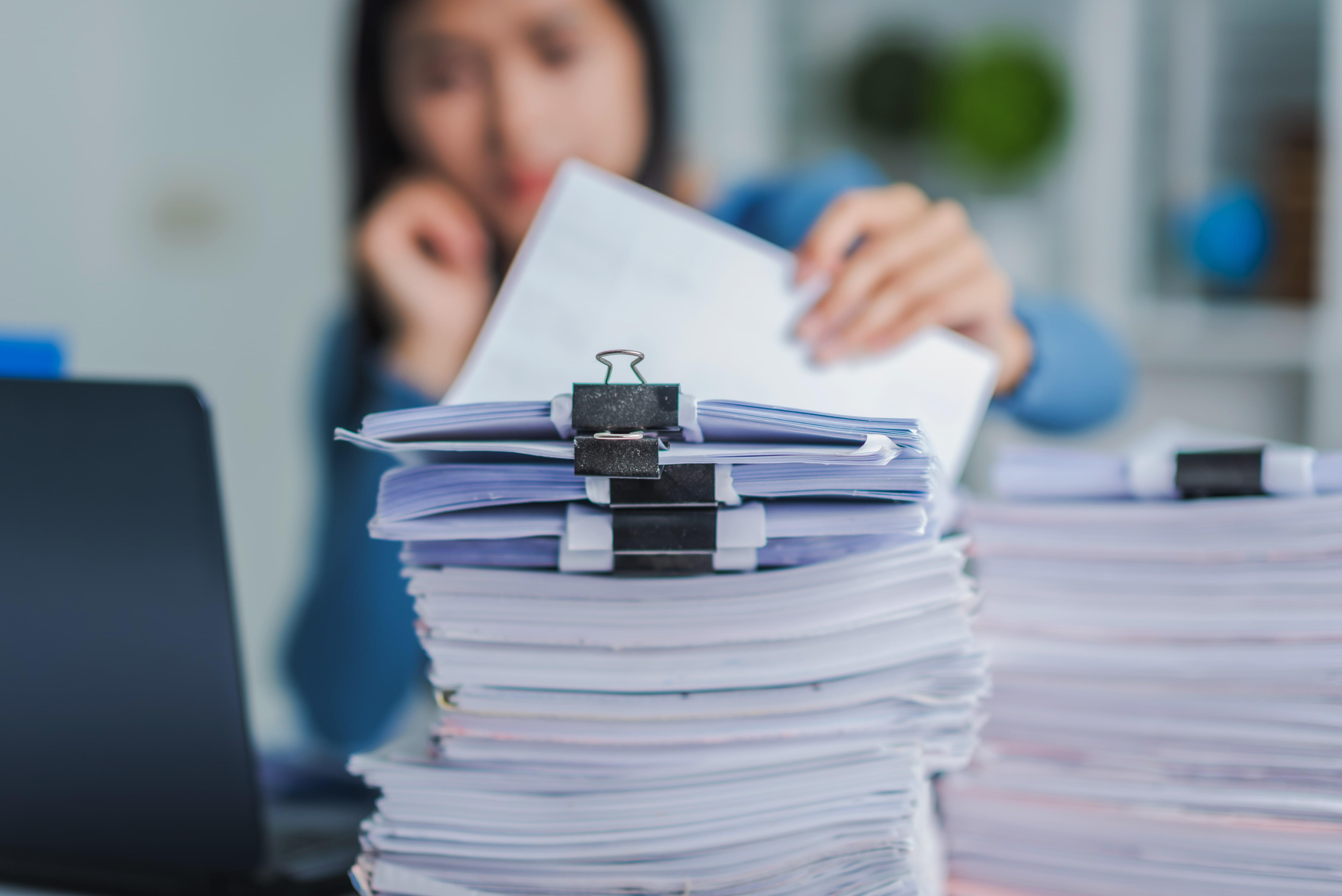
2020/11/20公開2022/4/01更新
環境保全やコスト削減の観点から推し進められているペーパーレス化。コロナ禍で在宅勤務が広がったことにより、ペーパーレスの必要性は一層高まっています。
この記事では、ペーパーレス化のメリットやデメリットとともに、ペーパーレスを推進すべき理由についてお伝えします。
目次
ペーパーレス化とは
ペーパーレス化とは、ビジネスシーンで使用する紙の資料を可能な限り電子化することです。紙の使用量低減による経費削減、地球環境保護、業務効率化などを目的としています。
ペーパーレス化が必要な理由
近年労働力人口の減少に伴い、限られた労働力を最大限効率的に活用する働き方改革が必要となっています。ペーパーレス化もその取り組みの一環として組み込まれており、効率性の向上という観点から見ると現場だけでなく経営者目線からも重要な取り組みです。昨今は在宅勤務やモバイルワークなどのテレワークを推進している企業も増えてきましたが、資料の電子化が進むことでより円滑にテレワークを実施できます。
紙による文書管理は、情報伝達手段として優れていますが、現場では間接作業として印刷、捺印、確認等の業務負荷が生じます。本来の仕事に充てるべき時間的資源がこれらに割かれており、効率性を下げている要因となっています。
ペーパーレス化を実現した場合、紙による文書管理によって割かれていた時間を別の仕事に充てることができます。
またペーパーレス化には効率性の向上以外にも保管スペースの削減が可能です。ペーパーレス化を実現した場合、文書は電子化されるため、文書へのアクセスはPCなどの電子機器があれば十分であり、文書管理のために会社に出社する必要がなくなります。
ここからは、さらに詳しくペーパーレス化について解説していきます。まずはペーパーレス化の事例を見たいという方は、こちらからZAC導入事例集 ペーパーレス化編をダウンロードなさってください。
ペーパレス化はなぜ進まないのか
企業における「業務改革取組状況」を分析した総務省 情報通信白書(平成24年度版)(*1)によると、ペーパーレス化の普及率は29.1 %であり、およそ3割にとどまっています。何が企業のペーパーレス化を妨げているのでしょうか? ペーパーレス化が進まない理由として次のような理由が考えられます。
- 社内の規定や制度が整備されていない
- 新たな社内ルールの構築が必須
- 一定の水準のITリテラシーが必要
社内の規定や制度が整備されていない
経営層が紙での管理を好んでいたり、実際の業務が忙しく業務プロセスの変更を行う余裕がないなど、体制を整えられていないことがあります。また、どのように整備すればいいか分からない、紙ベースの管理で困っていないからといった理由がペーパレス化を阻んでいると言えるでしょう。
新たなルールの構築が必須
ペーパーレス化を行うためには、電子ファイルの格納先、ファイル名などの社内ルールの取り決めが必須です。また賃貸契約書等書面等など法律で紙による保存が義務付けられている書類もあり、ペーパーレス化への障壁となっています。 しかし近年ではペーパーレス化の推進のために電子帳簿保存法が改定されペーパーレス化への風向きも変わってきています。
一定の水準のITリテラシーが必要
書類を電子化した際には、サーバーへのアクセスの仕方や、クラウドサービスへのログイン、セキュリティの知識などのITリテラシーが必要になります。 これらの知識はPC操作を日常的にどの程度行っているかに関わってくるために、社内でITリテラシーに濃淡が生まれます。心理的な抵抗があるケースもあり、会社全体でペーパーレス化に対する足並みが揃わない原因にもなります。
ペーパーレス化の4つのメリット
導入時の障壁を考えると躊躇してしまいそうなペーパーレス化ですが、メリットとデメリットをしっかり理解することが大切です。ペーパーレス化で得られるメリットとしては、以下の4点が考えられます。
①コスト削減
- 用紙、トナー代
- プリンタのリース代
- プリンタのメンテナンス費用
- 書類の管理費用(保存、破棄など)
電子データをメールで送るようになれば、書類の郵送料も必要ありません。機密情報が印刷された書類を廃棄するためのシュレッダーも不要になるため、オフィス機器にかかっていた費用を減らすことができるのです。また、書類を印刷するための人件費も削減できます。
②業務の効率化
たとえば過去の書類が必要になって探す場合、紙であれば一枚ずつ確認しなければならないため時間がかかってしまいますが、電子化すればキーワード検索で見つけることができるようになります。また、資料へのアクセスや、アップロード、共有も場所を選ばずできるようになるため、オフィスへの移動時間を削減して効率的に仕事を進められます。書類をバインダーにファイリングしたり、そのバインダーを整理するための手間もかからないので書類整理の手間も不要です。
③オフィスの省スペース化
印刷した書類はキャビネットなどに保管する必要がありますが、電子データならサーバー上に保管できるためオフィスを省スペース化することができます。書類の保管に使用するバインダーや収納BOXなども不要になりますので、スペースを有効活用できるようになるのです。
④紛失や劣化のリスク低減
紙の書類は、紛失や火災、水害による消失のリスクがありますが、電子化すればそのようなリスクを大きく減らすことができます。経年劣化で文字が消えて読めなくなるということもありません。データを保管しておくサーバーは厳重に管理しなければなりませんが、半永久的に保管ができるようになるのです。また、データにセキュリティ対策を施しておけば、端末を紛失しても機密漏洩のリスクは低くなります。
ペーパーレス化の3つのデメリット
上述のように多くのメリットがあるペーパーレス化ですが、導入することによるデメリットも考えられます。それが次の3つです。
①導入費用がかかる
ペーパーレスを導入するためには、電子化された資料を読むための端末(個人用パソコンやタブレット、スマートフォン)と、データを送受信するためのネットワーク整備が必要です。多くのデータを保管するのであれば、大容量のクラウドやサーバーを契約しなければならず、定期的に利用料がかかります。また、現時点で大量の紙の資料があり、それらをスキャナーなどで電子化する場合は、工数が大きく膨らみます。
②視認性が落ちる
電子化された資料は拡大して読むことができる反面、全体像を把握することが難しくなる場合があります。特に、大きな図面や字の細かい書類などは、読む際に拡大比率を大きくするほど画面に表示できる範囲が狭まります。デジタル端末が一つしかなければ、複数枚の資料を見比べづらいこともあるため、作業効率が落ちる可能性も考えられます。
③システムや機器の故障リスクがある
紙のような劣化や破損はないものの、書類を保管するためのサーバーが故障したりシステム障害が起こったりした場合、閲覧できず業務に支障をきたします。故障の度合いによっては、データが消失するという最悪のケースも考えられます。そのため、頻繁にバックアップを取ったり複数の場所に保管するなど、あらかじめ対策を考えておくことが必要です。
最初大変でもペーパーレス化を推進すべき
ペーパーレス化には導入時にさまざまなコストがかかります。それでも推進すべきなのは、不測の事態が起きたときに従業員の安全確保と事業継続を両立させるためです。書類紛失や情報漏洩への対策など、企業としてのリスクマネジメントとして効果の高いペーパーレス化ですが、昨今の社会情勢を鑑みてもその導入は避けられません。 2020年には新型コロナウイルスが流行し、緊急事態宣言が発出されました。台風などの自然災害も年々被害を増しています。そうした事態に際しても、ペーパーレス化が進んでいれば従業員の安全を確保しながら事業を継続することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査によると、東京23区で就業している回答者のうち、コロナ禍においてのテレワークを行った人は、55.5%(*2)となっており、多くの企業でテレワーク在宅勤務が取り入れられました。 これを機にテレワークとともにペーパーレス化を促進した企業として株式会社ノーリツが挙げられます。同社では緊急事態宣言発令以降、契約書類や代表者印の電子化を進めて従業員の在宅勤務を推進しています(*2)。
とはいえ、どの企業もすぐにペーパーレス化ができたわけではありません。株式会社ROBOT PAYMENTが実施する「日本の経理を自由に」プロジェクト(*4)によると、経理に携わる回答者の約7割がテレワークを実施できなかったことが調査によって明らかになっています。その背景には、契約書や請求書など、慣習的に紙で管理していた書類のやりとりや押印のために出社しなければならなかったことがあります。 導入のハードルがあったとしても、社員を思い、滞りなく業務を続けるために、ペーパーレスを推進する必要があるのではないでしょうか。
ペーパーレスでSDGsに貢献
近年、ニュースでも話題になっているSDGs(=Sustainable Development Goals)(*5)は、2015年に国連サミットで採択された国際目標です。持続可能な開発のため、世界中の全ての国に行動が求められており、日本でも各企業が積極的に取り組んでいます。 SDGsには、17個のゴールと169個のターゲットが設けられており、ペーパーレス化は以下のゴールに該当すると考えられます。
出典:外務省:SDGsとは?
- 8「包摂的かつ持続可能な経済成⻑及びすべての⼈々の完全かつ⽣産的な雇⽤と働きがいのある⼈間らしい雇⽤(ディーセント・ワーク)を促進する」
- 12「持続可能な⽣産消費形態を確保する」
- 13「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」
- 15「陸域⽣態系の保護、回復、持続可能な利⽤の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに⼟地の劣化の阻⽌・回復及び⽣物多様性の損失を阻⽌する 」
つまり、ペーパーレス化を推進することは企業としてSDGsに取り組むことだといえ、その意味では社会のために必要な行動だともいえます。
マインド×仕組み、両面からペーパーレス化を推進
今後、働き方改革や非常時の対応でペーパーレス化はますます加速していくと考えられます。コロナ禍によって、テレワークに移行できない状況に危機感を抱いた企業は少なくないはずです。さらにSDGsの観点から、ペーパーレスで環境保全に貢献することが企業の責任の一つになるでしょう。
ペーパーレス化の重要性を踏まえたうえで、実際に導入する際に大切な条件がふたつあります。ひとつはマインドです。ペーパーレス化の必要性や取り組む意義を社内に周知した上で、トップや従業員のマインドを変えていかなければなりません。ふたつ目は、ペーパーレスで業務を遂行するための仕組みです。必要なツールの導入と明確な運用ルールを決めることで、不慣れな人でも業務をしやすい状態をつくる必要があります。
ペーパーレス化推進の手順
マインド×仕組みでペーパーレス化を推進していく上では、以下のような手順で進めていくと良いでしょう。
- 経営陣のペーパーレス化の理解を深めてもらう
- 経営陣から発信してもらう
- 保存要件の確認
- ルールの構築を行う
①経営陣のペーパーレス化の理解を深めてもらう。
上記で紹介したように、ペーパーレス化が進まない理由のひとつは社内の制度や慣習が整備されていないことです。そのため、まずは権限を持つ経営陣のマインドを変える必要があります。
②経営陣から発信してもらう
経営陣の理解を得たのちに「ペーパレス化を推進していくこと」を発信してもらいます。トップダウンにより社内で一丸となってペーパーレス化を推進していくことができます。
③保存要件の確認
各部署で取り扱っている文書の棚卸しを行い、法令で定められている保存要件を確認します。なかには紙での保存が必要な文書もあるため、注意が必要です。
ペーパレス化の推進に欠かせない電子帳簿保存法については下記の関連記事をご覧ください。
④ルールの構築
ペーパーレス化に向けて、機密性などの観点から文書管理のルールを取り決めます。そして、社内規定として管理職から発表し、権威を持たせます。文書管理に関してはマニュアルの作成なども必要となる場合もあります。
⑤紙による管理をしていた文書のペーパーレス化を行う
ペーパーレス化の方法としてスキャンが一般的です。スキャンしたデータは、フォルダに分け、ラベリングを行います。この作業は、社員のリソースを取ることになるでしょうります。そのため、ペーパーレスにスキャニング代行サービスを利用するのも良いでしょう。
⑥必要に応じたツールやシステムの導入
タブレット端末などのハードウェアを支給することで持ち運びと操作面の優位性が確保されます。ただしネットワークの環境構築などは事前に決めておく必要があります。電子文書の保管方法には検索性の高いクラウドサービスの導入もおすすめです。 ※文書量によって利用料も変わる場合が多いので、どの文書を電子文書で管理するのか取り決めが必要です。
まとめ
企業や職種によってペーパーレス化の難しさは異なりますが、まずは社内の一部の資料から電子化するなど、徐々に導入していくことがおすすめです。トップダウンで進めながらも、現場の声を取り入れて、現実的かつ継続可能なペーパーレス化に取り組んでいきましょう。
参考文献
*1:総務省 情報通信白書(平成24年度版)
*2:内閣府:「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
*3:株式会社ノーリツ、コロナ禍で従業員の新しい「働き方」を促進 在宅勤務拡大のためペーパーレス化促進プロジェクトを発足
*4:株式会社ROBOT PAYMENT (ロボットペイメント)、「日本の経理をもっと自由に」プロジェクト
*5:環境省:「すべての企業が持続的に発展するために- 持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド -」